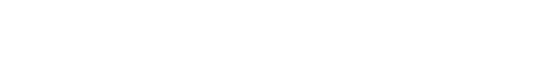M&Aの企業価値評価(バリュエーション)には、いくつもの手法があります。
その中でも、最もよく用いられている方法の一つがDCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)です。
DCF法はファイナンス理論に裏付けされており、M&Aはもちろんのこと、それ以外にも実際に多くの現場で利用されている方法でありながら、実際の売買価格との乖離がひどく、DCF法によってM&Aの価格が決まることはまずありません。
そこで本日は、難解複雑なDCF法の計算方法をできるだけ数式を使わず感覚的に理解していただき、DCF法のメリットとデメリットを踏まえた上で、結局DCF法とは何なのかを解説していきたいと思います。
DCF法とは何か?
DCF法とは「Discounted Cash Flow Method」の略語で、割引計算されたキャッシュフローという意味を表しています。
日本語で「キャッシュフロー割引法」と言われることもあります。
企業価値の測定方法はさまざま
企業価値を測る場合、その測定方法にはさまざまなアプローチが存在します。
たとえば、対象企業の純資産を基に企業価値を算定する方法(コストアプローチ)があります。
また、上場している類似業種と比較して企業価値を算定する方法(マーケットアプローチ)もあります。
そして、将来生み出す収益を基に企業価値算定する方法(インカムアプローチ)などもあります。
DCF法は、このような企業価値を測定するための手法の一つで、インカムアプローチにより企業価値の測定する場合に用いられています。
DCF法の計算方法
DCF法とは、簡単に言うと何らかの方法(後ほど詳しくご説明します)で将来生み出す毎年の収益を算出し、それを合計して企業価値を算定する方法のことをいいます。
もう少し細かくお話しすると、企業が将来生み出すキャッシュフロー(収入)を現在の価値に換算(これを「割引計算(Discount)」といいます)し、それを合計したものをDCF法といいます。
ここで大切なのは、「割引計算」を行うという点です。
たとえば、来年10万円もらえる権利があるとしたら、一体いくらで売れるでしょうか?
多分、多くの人は10万円より少ない金額を提示するのではないでしょうか?
では仮に、100年後に10万円もらえる権利があるとしたらどうでしょうか?
ほとんど値段がつかないか、もしくは誰もそんな権利は買わないかもしれませんね。
このように、将来のお金を現在の価値に換算すると、必ず少ない(割り引かれた)金額になります。
これを割引現在価値といいます。
この考え方を用いて、企業が生み出す毎年のキャッシュフローを現在価値に割り引いて合計する評価方法のことをDCF法といいます。
どうしてDCF法が重宝されるのか?
DCF法は、M&Aの企業価値評価だけで使われているわけではありません。
たとえば不動産価値の鑑定においてもDCF法が用いられています。
DCF法がこのように、資産全般を評価する場合に多分野で用いられているのはなぜなのでしょうか?
それは、DCF法をコストアプローチやマーケットアプローチの手法との比較してみるとよく理解できます。
コストアプローチは対象企業の純資産価値をベースにのれん代を加えたものを企業価値とします。
こののれん代は、通常営業利益の3~5年分で評価されることが多いですが、これには論理的な裏付けや数式などは一切ありません。
実は、何の根拠もない数字なのです。
いっぽうマーケットアプローチの場合は、上場企業の類似業種と比較して企業価値を評価するのですが、そもそも同業であっても単純に事業規模だけで企業の価値を測ることはできません。
また、マーケットアプローチでは特定企業の競争力や成長見込みを企業価値に織り込むことは出来ません。
つまり、こちらの手法にも論理的な裏付けや理論に基づく数式などは一切ありません。
この2つの評価方法と比べると、DCF法は最新のファイナンス理論に裏付けられているため、多くの場所で活用されているのです。
DCF法は評価額を算出しているわけではない
DCF法で算出された金額は、価格ではなく企業の価値です。
そもそも、DCF法で算出された金額でM&Aが行われることはまずありません。
価格は需要と供給によって成立するものであり、その点では本質的な価値とは関係なく成立するものです。
企業の収益性という観点から企業価値を測定した場合、どうなるのかを測定するのがDCF法です。
ですから、A社とB社を比較した場合、DCF法ではA社の企業価値の方が高いけど、コストアプローチで評価した場合は逆にB社の方が企業価値が高いということも起こりうるわけです。
DCF法を正しく理解するための3つのルール
DCF法がどのようなものなのか、ざっくりと理解していただいたところで、今度はもう少し深く掘り下げてみましょう。
DCF法を理解するためには、DCF法が成り立つためのお約束(ルール)が3つあります。
そのルールについてお話しします。
ルール① あらゆるモノの価値は将来得られるキャッシュフローによって決まる
DCF法が成り立つ世界では、あらゆるモノの価値は、それを所有したことにより将来得られるキャッシュフローの総和によって決まります。
普通の感覚だと、値段の高いもの(ブランドバックなど)に価値があると考えますが、DCF法の世界では、将来得られるキャッシュフローが高額なものに価値があると考えます。
たとえば、最新設備を持っている工場はDCF法でも(事業計画書作成時に)高い評価が付きますが、これは処分価格が高くなりそうだから高いのではなく、当分の間修繕や設備投資が必要なく、収益がかなり期待できそうだから高いのです。
将来キャッシュフローの計算方法
事業が生み出す将来のキャッシュフローのことを、FCF(フリーキャッシュフロー)といいます。
FCFは、営業活動によって生み出された営業キャッシュフローから、事業を維持するための設備キャッシュフローを引くことにより算出することが出来ます。
- FCF=「営業キャッシュフロー」-「設備キャッシュフロー」
ルール② 将来得られるキャッシュフローは現在の価値に換算される
前章でもお話ししたように、将来得られるお金を現在の価値に換算すると、必ず割り引かれて少ない金額になります。
DCF法によって算出された将来のキャッシュフローも同様で、必ず現在価値に割り引かれるため割引率に応じて少しだけ少ない金額になります。
そして、将来に行けば行くほど金額はどんどん少なくなり、最終的には限りなくゼロに近づいていきます。
別の言い方をするなら、現在の100万円と1年後の110万円を等価とするのがDCF法の考え方なのです。
ところでFCFは何年先まで計算すれば良いのか
ところで、FCFはいったい何年先まで計測していけばよいのでしょうか?
・・・答えは「永遠」です。
永遠にはるか先の将来までFCFを毎年積み上げていったら企業価値が無限大に大きくなると思われるかもしれませんが、実際は違います。
上述のように、将来キャッシュフローを現在価値に割り引く場合、将来へ行けば行くほど限りなくゼロに近づいていくため、企業価値が無限大になることはありません。
また、割引率が高ければ高いほど、FCFが限りなくゼロに近づくまでの期間が早くなります。
ルール③ 割引率は期待リターンによって決まる
たとえば、イチかバチかの事業に資金を投下する場合、どれくらいの利益が求められるでしょうか?
おそらく誰でもハイリターンを望むはずです。
なぜなら、リスクとリターンは必ず背中合わせの関係にあるからです。
DCF法における割引率も、これと同じ考え方をします。
事業のリスクが高い場合、将来の割引率が高くなります。
非常にリスクが高く、どうなるかわならないような事業であれば、期待リターンが非常に高くなるため割引率も同様に高くなります。
このような場合は、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いていくと、あっという間に消えそうなくらい小さい金額になってしまいます。
言い換えると、DCF法の割引率は投資リスクの高さによって決まるとも言えます。
この章でご紹介した3つの考え方に基づき、DCF法は成り立っています。
それでは次は、将来キャッシュフローと割引率がどのように算出されるのかについて解説していきます。
ターミナルバリューと割引率の求め方
「DCF法におけるFCFは永遠に遥か先の将来まで計算する」と前章でお話ししました。
しかし、実際にDCF法を使う場合には少し違う計算方法で企業価値を算出します。
ターミナルバリューという考え方
企業の業績を予測する場合、どれだけ頑張っても何十年も先まで予測することは不可能です。
せいぜい3~5年先までを予測するので精一杯です。
そこで、3~5年先までは事業計画に基づいて予測されるFCFを利用し、そこから先の、個別にキャッシュフローの試算が出来ない期間に関しては、「毎年〇〇万円のFCFが生まれると仮定して、割引計算を行い集計していきます。
この、事業計画に基づかない個別にキャッシュフローの試算ができない期間(つまり、3~5年後以降)の企業価値のことを、ターミナルバリューといいます。
実際にDCF法で計算する場合は、まず事業計画を立案してある程度予測できる範囲内は予測に基づくFCFによりDCFを行い、そこから先は概算でざっくりと行い、最終的にはその2つを合計することにより企業価値を算出するわけです。
割引率の求め方
ここまでの説明で、何となくDCF法による企業価値の算出のしかたはご理解いただけたと思うのですが、これも、割引率によって結果は大きく左右されます。
FCFを現在価値に割り引く割引率は、加重平均資本コスト(WACC)によって算出することができます(注)。
(注)WACCを使った割引率の計算は非常に難解なため、経営者ご自身が計算されることはまずないと思います。ここでは、「何らかの方法で将来の価値を現在の価値に置き換えるための割引率を計算するんだな」という程度の理解で十分です。
DCF法のメリット・デメリット
では最後に、DCF法のメリットとデメリットをまとめてみます。
DCF法のメリット
DCF法のメリットは、以下のようになります。
メリット① 会社の企業価値を正確に算定しやすい
DCF法は、しっかりとしたファイナンス理論に基づく計算によって企業価値を算出するため、他の方法と比べてはるかに論理的で正確な企業価値を算定できると言えます。
メリット② 割引率の計算にある程度の幅を持たせることが出来るため、状況に応じて柔軟に対応することができる
DCF法は、事業計画の策定時はもちろんのこと、割引率を計算する場合も、最終的にはある程度の幅を持たせて算出します。
したがって、状況に応じて企業価値評価を柔軟に行うことができます。
DCF法のデメリット
いっぽう、DCF法のデメリットは以下のようになります。
デメリット① 何となく論理的な方法に思えるが理解するのが難しい
インカムアプローチやマーケットアプローチなどと比べると、DCF法は直感的に理解するには難しく、「何となく論理的な評価方法には思えるけど、他の方法と比べるとどうもピンと来ない」と感じる方が多いです。
デメリット② 算定時に数値調整の幅があるため、DCF法を使う人が恣意的な結果に導くことができてしまう
DCF法は計算の過程でいくつもの調整を行うことが出来るため、DCF法を行う人のさじ加減ひとつで、どのようにでも結果を変えることができます。
そのため、DCF法そのものに本当に客観性があるのか疑問視される場合があります。
このように、DCF法は他の評価方法と比べるとロジカルに企業価値評価を行うことが出来る半面、評価者のさじ加減一つでどのような結果にでも導くことができるという面を持ち合わせています。
まとめ
DCF法は数多くある企業価値評価の方法の中で最も頻繁に活用されているものの一つで、他の手法と比べるとはるかに論理的に企業価値評価を算出することができます。
しかし、DCF法によって算出された企業価値も一つの理論値に過ぎず、最終的な価格は売り手と買い手の話し合いによって決着します。
M&A市場で自社の価格が一体どれくらいなのかを知りたい方は、是非一度M&Aに詳しい専門家に問い合わせてみて下さい。
事業承継・M&Aについてわからないことがあるときは
事業承継・M&Aについて不明点があれば、契約書作成やM&Aについて知識のある専門家に相談すれば安心です。
『経営者コネクト』にご相談いただければ、知識が豊富な専門家がアドバイスいたします。
M&A前の経営戦略の見直しやマーケット調査、M&A後の経営統合までの長期的なスケジュール策定などもサポートします。
気になる方は、『お問い合わせフォーム』よりご連絡いただければ、無料でご相談をお受けいたしますのでお気軽にお問い合わせください。