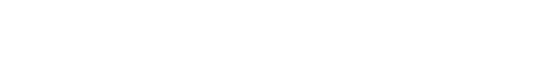M&Aで対象企業の企業価値を評価する時に、時価純資産法と並んで最も用いられている方法の一つにDCF(ディスカウントキャッシュフロー)法があります。
DCF法とは、企業が生み出す将来キャッシュフローに着目し、現在価値に割り戻した総和を企業価値とする方法なのですが、その割り戻す時に用いられているのが「WACC(ワック)」と呼ばれる割引率です。
WACCが変わるだけで企業価値評価が大幅に変わるため、WACCはDCF法の要となるとても大切な数字なのですが、計算方法が難しいため、まだまだ正しく理解されているとは言い難い状況にあります。
そこで本日は、DCF法がはじめての人はもちろんのこと、今までWACCがよく分からなかった人やもう少しDCF法を詳しく知ってみたい人などを対象に、WACCとDCF法の関係や企業価値評価とM&A価格との関係などについて、できるだけ分かりやすく解説してみたいと思います。
WACCを知る前に:将来キャッシュフローと資本コストについて
WACCやDCF法の説明をする前に、まず将来キャッシュフローと資金調達コストの関係からお話ししてみたいと思います。
あなたならどちらを選びますか?
いきなりですが、今100万円をもらえる権利と1年後に100万円をもらえる権利、あなたならどちらを選びますか?
ほとんどの人は、今100万円をもらえる権利と選びますよね。
では少し設定を変えて、今100万円をもらえる権利を100万円で買うのと、1年後に100万円もらえる権利を95万円で買うのだったらどうでしょう?これなら少し迷うのではないでしょうか?
なぜなら、将来のお金の価値は今のお金の価値とは等価ではなく低いためです。
この例のように、将来の収入(=1年後に100万円もらえる権利)を現在の価値(=95万円)に換算することを「割り引く」といい、割り引いたことにより算出された価値のことを「割引現在価値」といいます。
ですから、この割引率さえ決まれば、100年後に100万円をもらえる権利がいくらになるのかも簡単に計算することができます。
割引率は投資リスクによって変化する
先ほどの例の続きで、1年後に100万円をもらえる権利を2人の人が95万円で売っているとします。
1人は一部上場企業の社長で、そしてもう一人が素性の良く分からない人だったとしたら、あなたはどちらからその権利を買いますか?
おそらく、ほとんどの人は前者を選ぶでしょう。
では、後者のがその権利を30万円で売っていたらどうですか?少し悩みませんか?
これは投資の基本で、投資リスクが高ければそれに応じて求めるリターン率も高くなるためです。
前者は1年後の100万円を95万円に割り引く程度でその権利を売ることができますが、後者は100万円を30万円にまで割り引かなければ売買成立が難しい(=割引率がかなり高い)わけです。
つまり、割引率は投資家の期待リターンによって決まるため、「割引率=期待リターン」
となります。
この、お金を出す人から求められる期待リターンのことを「資本コスト」といいます。
DCF法におけるWACCとは、この割引率(=投資家などから求められている期待リターン)に他なりません。
何らかの方法で企業にお金を出している人たちから求められている「1年後にこれくらいもらわないと割に合わないな」と思われている期待リターンがWACCの正体です。
WACCを使って将来のキャッシュフローを割り引いていくと、1年後の将来キャッシュフローの割引現在価値は〇〇円、2年後の将来キャッシュフローの割引現在価値は〇〇円、という具合に1年ごとの将来キャッシュフローを求めることができます。
DCF法における企業価値とは、こうやって求めたキャッシュフローの割引現在価値を合算することで算出することができます。
なお、「算出するキャッシュフローはいったい何年先まで?」と疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、答えは「永遠に」です。
DCF法における将来キャッシュフローは基本的に毎年同じ額に設定する(ただし3~5年程度先の予測可能な将来については変動させます)ため、将来キャッシュフローの割引現在価値は先へ行けば行くほど少なくなっていきます。
そして最終的には限りなく0円に近づいていくため、永遠に将来キャッシュフローを合算していっても企業価値が無限大になることはないわけです。
資本コストの構成とWACCの具体的な計算方法について
前章において、資本コストとは(企業に)お金を出した人が求める期待リターンであるというお話をしましたが、この資本コストは実は2つに分かれています。なぜなら企業にお金を出す人は2種類に分けることができるからです。
2種類の資本コストの正体と割引率の違い
会社が資金を外部から調達する場合、その選択肢にはおもに2つの方法が考えられます。
一つは株式を発行して株主から資金を調達する方法で、もう一つが金融機関から借り入れをする方法です。
前者で調達した資金に求められる資本コスト(=期待リターン)を株主資本コストといい、後者で調達した資金に求められる資本コスト(=期待リターン)を負債コストといいます。
具体的には、株主資本コストとはおもに株主に支払う配当のことを指し、負債コストとはおもに借入金の支払利息のことを指します。
ほぼすべての企業は、株主からも金融機関からも資金を調達しているため、どの企業の資本コストも、株主資本コストと負債コストの2種類が混じり合った状態で資本コストを構成しています。
資本コストが常に混じり合う理由
企業が金融機関から資金の借り入れをする場合、返済期限や返済方法を約定した上で担保などの提供が求められます。
また、仮に会社が倒産した場合でも、財産の分配を株主に先んじて受けることが出来ます。
いっぽう株主は、業績が悪ければ配当金が支払われないだけでなく、会社が倒産した場合も、すべての債務を返済した後で残った残余財産が、出資金額に応じて按分されるだけです。
つまり、負債コストと比べると株主資本コストの方がリスクが高いため、一般的には負債コストの方が株主資本コストよりも低くなります。
では、資本コストを下げるため、資金調達はできるだけ負債コストに頼ればいいのかというと、実はそうでもありません。
自己資本と比べて有利子負債が増えすぎると自己資本比率が下がるため、倒産リスクが上がり、結果的に金融機関からの借入金の利率が上がってしまうからです。
このような理由により、資本コストは株主資本コストと負債コストの両者が常に混じり合った状態で構成されているのです。
2つの資本コストを加重平均した数字がWACC
資本コストを構成している株主資本コストと負債コストは、先ほどお話ししたように投資リスクが違うため、それに応じて期待リターンもそれぞれことなります。
そのため、この2種類を混ぜ合わせた状態の資本コスト(=期待リターン)を求めるため、両者を加重平均しなければなりません。
両者を加重平均して算出された数字がWACCとなります。
具体的には、以下の算式によってWACCを求めることができます。
WACC=rE×E/(D+E) + rD(1-Tc)×D/(D+E)
- rE:株主資本コスト
- rD:負債コスト(金利)
- E:株主資本
- D:負債
- Tc:実効税率
この式だけ見ていると「何だこれは?」と思われるかもしれませんが、株主資本コストと負債コストをそれぞれの時価で加重平均しているだけです。
また、負債コストの部分に実効税率が出てくるのは、支払利息が増えれば増えるほど節税効果が発生するため、その影響を排除するためです。
WACC算出における株主資本コスト(rE)の求め方
さて、上述のWACCを求める算式の中で、まだ数字が定まっていないのが株主資本コスト(rE)の部分です。
負債コストとは違い、株主資本コストには明確な数値は存在しません。
なぜなら株主が求める期待リターンは株主ごとにそれぞれことなるからです。
そのため、株主資本コストは以下の算式によって求めます。
rE=rF+β(rM – rF)
- rF:リスクフリー商品の利回り
- β:株式のベータ値
- rM:株式市場全体の資本コスト
この式はWACCの式よりも難しそうに見えますが、以下の3段階の計算を行って株主資本コストを求めています。
- 株式市場全体の資本コストを求める
- 対象となる会社が、①で求めた株式市場の資本コストと比べて何倍くらいリスキーかを求める
- ②で求めた倍率分だけ資本コストを増やす
それでは、各工程をもう少しだけ掘り下げて見てみましょう。
①株式市場全体の資本コストを求める
rM(株式市場全体の資本コスト)は、長期のTOPIX変動分析から推計して求めます。これにはかなりの時間と特別なノウハウが必要なため、通常は経済調査会社に依頼して算出してもらいます。
次にrFとは、限りなく無リスクの商品の利回りのことを指します。一般的には10年物国債の利回りを用います。
株主計算コストの式の後半部分の(rM – rF)とは、株式市場全体の利回りから無リスクでも得られる利回りの影響を排除した純粋な株式市場の資本コストを意味しています。
②対象となる会社が、1で求めた株式市場の資本コストと比べて何倍くらいリスキーかを求める
TOPIXが1%下がった時、対象会社が2%下がれば対象会社は株式市場の資本コストと比べて2倍リスキーであることになります。このリスク度の倍率を表す係数が上の式のβです。
対象企業が非上場企業の場合、類似業種を営む上場企業数社のβ値を参考にして求めます。
③2で求めた倍率分だけ資本コストを増やす
最後に、2で求めた倍率分だけ資本コストを増やします。具体的には、リスクフリーの利回り(10年物国債の利回り)rFにβ(rM – rF)を足します。
これで、rE=rF+β(rM – rF) を求めることができます。
なお、この数式のことをCAPM(キャップエム)といいます。
WACCについての説明は、これで終わりです。次章では、このWACCを用いて実際にDCF法を用いた企業価値の算出手順について解説します。
WACCを用いたDCF法による企業価値の算出手順
それでは最後に、WACCを用いたDCF法で、実際に企業価値を算出していく手順について解説していきます。
手順1.事業計画書から3~5年分のフリーキャッシュフローを見積もる
事業計画書を作成し、今後3~5年間分のフリーキャッシュフロー(以下「FCF」)を見積もります。FCFとはWACCで割り引くための事業の将来キャッシュフローのことをいいます。
なお、FCFは以下の式により算出します。
手順2.WACCを算出し、割引率を決定する
本記事でこれまでご説明した手順でWACCを算出し、割引率を決定します。ただし非上場企業を評価する場合は上場企業と比べて投資リスクが増えるため、通常は資本コストを3~10%程度加算します。これをサイズプレミアムといいます。
手順3.毎年のキャッシュフローをWACCで割り引いて合計する
事業計画書を参考に、計画最終年度以降の平均的な年度キャッシュフローを概算します。
通常は最終年度の数字をそのまま引き継ぎます。
事業計画書に記載した3~5年分のFCFと6年以降のFCFをすべてを、手順2で算出したWACCで割り引いて合計していきます。
具体的には、
(1年目のFCF)/(1+WACC)+(2年目のFCF)/(1+WACC)²+(3年目のFCF)/(1+WACC)³+・・・・・・
の計算を行い算出します。
これでDCF法による事業価値の算出は完了しますが、これを基に株価を算出する場合は、さらに非事業資産等を加算した後で有利子負債を控除し、発行済み株式総数で割って1株当たりの株価を算出します。
まとめ
本日は、DCF法で企業価値評価を行う際に最も大切なWACCについて、その内容や具体的な計算方法をかなり掘り下げてお話ししてみました。
DCF法はM&Aの現場で最も用いられている企業価値評価の方法のひとつであり、企業同士の企業価値を測る方法としては、現代ファイナンス理論に裏付けられた理論的に最も完璧な方法と言うことができます。
ただし、DCF法によって算出できるのは、企業や事業の価値であり、価格ではありません。
なぜなら価格は相対的なものであり、需要の高さによって上下するため、理論的な裏付けとは関係なく決定されるものだからです。
そのため、M&Aにおける自社の相場や具体的な価格等を知りたい方は、アドバイザーなどの専門家に是非一度ご相談ください。
企業価値評価に悩んだら
 経営者コネクト
経営者コネクト事業承継の方法や後継者が決まっていなくても、まずは無料相談が可能です。
お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。